江戸時代の日本では、言葉を学ぶための重要な辞書として「節用集」が広く使われていました。漢字の読み書きや語彙の学習に役立つこの辞書は、室町時代に生まれ、その後、江戸時代に改訂・増補が重ねられました。庶民から学者まで幅広い層に利用され、教育や識字率向上にも貢献した「節用集」。今回は、その特徴や収録されている言葉、文化的背景について詳しくご紹介します。
大河「べらぼう」に出てきた節用集とは?
「節用集」(せつようしゅう)は、日本の江戸時代に作られた、
日本語の辞書の一種です。
特に漢字の読み書きや語彙を学ぶための学習書として利用されました。
「節用集」の生みの親と発展の歴史
「節用集」は、室町時代の僧侶 戦国時代の学僧・人文学者の饗庭範忠(あえば のりただ) によって編纂されたとされています。
彼が15世紀後半に最初の版本を作成し、
その後、江戸時代にかけて多くの改訂・増補が行われました
特定の一人の著者によるものではなく、
時代ごとにさまざまな学者や出版者が手を加え、
発展していった辞書です。
「節用集」は、日常生活に必要な言葉を幅広く収録しており、
漢字の読み方や使い方、
漢文の読み方なども解説されています。
まさに当時の百科事典のような役割を果たしていたと言えます。
節用集とは?節用集の内容
語彙の収録方法
節用集は、通常、漢字の部首や読み(五十音順)など
の順番で単語を整理していました。
現代の国語辞典のように詳しい語釈はなく、
簡単な説明や同義語が付けられることが多かったです。
実用的な内容
日常会話や手紙で使う言葉
商取引や職業関連の語彙
地名や人名の漢字表記
仏教・儒教・神道に関する用語
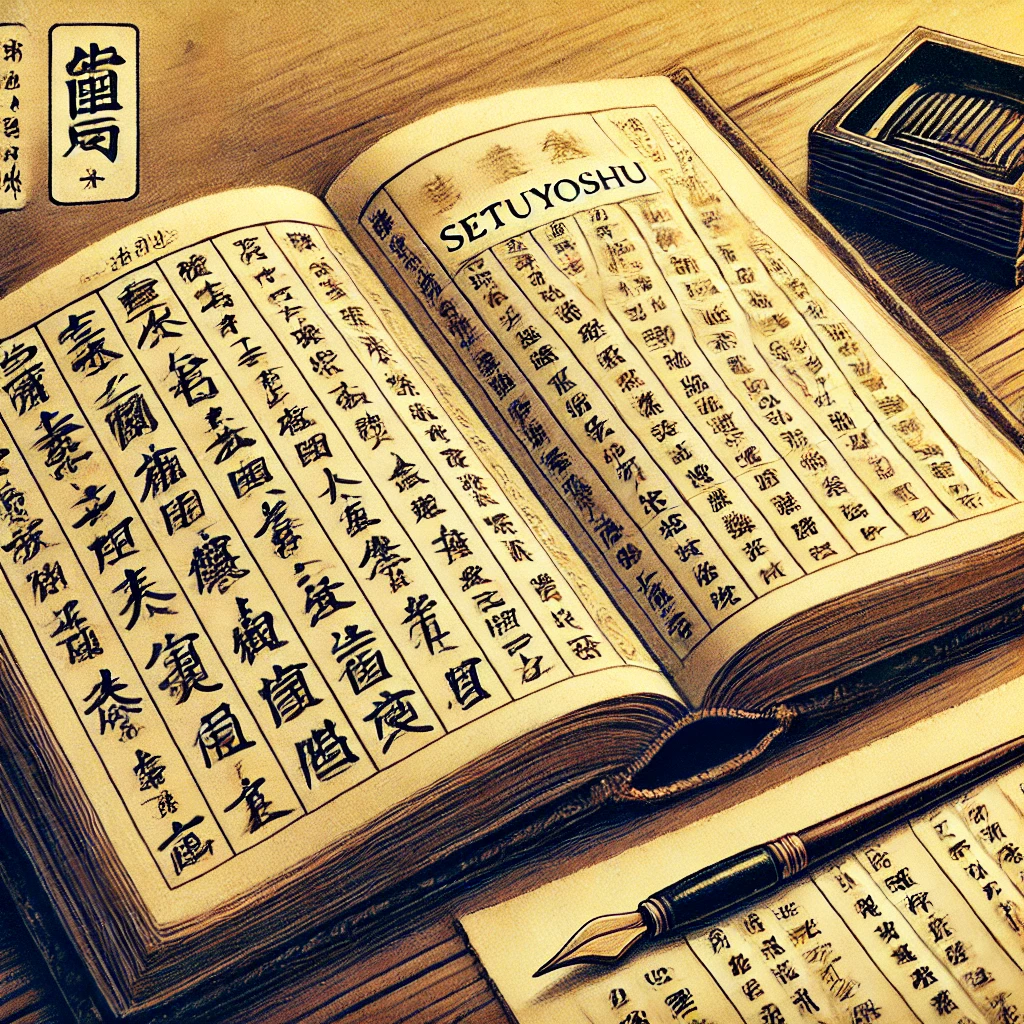
当時の人々にとって役立つ情報がまとめられていました。
節用集の主な版本と発展
吉文字屋本(京版本)
京都の書肆・吉文字屋が出版した版本は、優美な装丁と見やすい版面が特徴で、
武士階級や町人の子弟向けの教材として広く用いられました。
特に仮名と漢字を併用し、語彙ごとに意味や読みが添えられていたことから、
はじめて漢字を学ぶ子どもたちにとってわかりやすい構成でした。
須原屋本(江戸版本)
江戸の須原屋茂兵衛は、江戸版の代表的出版者の一人で、
『節用集』の普及に大きく貢献しました。
須原屋本では、実用的な語彙を多く含み、商人や職人たちの日常語に即した構成になっており、
江戸の庶民生活に即した語彙の選定がされていました。
これにより、『節用集』は読み書き教育の標準教材として江戸庶民に根付いたのです。
斬新な試み──蔦屋重三郎の『節用集』
18世紀後半、吉原を拠点とした名出版人・蔦屋重三郎は、
『節用集』にもその革新的な編集手法を導入しました。
それまでの節用集が語彙中心の実用書だったのに対し
、蔦屋版では美しい挿絵をふんだんに盛り込み、視覚的にも楽しめる語彙集へと進化させました。
これは単なる言葉の羅列ではなく、「読んで楽しい」「見て美しい」文化教材としての
一歩を踏み出した画期的な試みでした。
浮世絵師とのコラボ──喜多川歌麿や春章の筆も?
蔦屋本の『節用集』には、「花見」「雪遊び」「相撲取り」など、
季節の行事や庶民の暮らしを描いた浮世絵風の挿絵が添えられ、読者の理解を助けました。
とくに注目すべきは、その挿絵を喜多川歌麿や勝川春章といった
一流絵師が担当したとされることです。
こうした豪華なビジュアルは、学習書という枠を超えて『節用集』を
アート性の高い出版物へと昇華させ、広く庶民に親しまれるきっかけとなりました。
娯楽と教育を融合させた江戸の知的文化
蔦屋本の『節用集』は、家庭内での教育書として用いられる一方、
挿絵を通して会話や読み聞かせを楽しむ娯楽本としての役割も果たしていました。
さらに、当時の出版統制をすり抜ける工夫として、
さりげない風刺や洒落がちりばめられた表現も見られます。
こうした要素により、蔦屋版『節用集』は、
知識・芸術・風俗が融合した江戸文化の象徴的な書物となり、後世にもその価値を伝えています。
教育・識字率の向上に貢献
寺子屋教育と『節用集』──庶民に広がった学びの道具
江戸時代、日本の識字率は世界でも異例の高さを誇っていました。
その背景には、全国に広がった寺子屋教育の存在があります。
町人や農民の子どもたちは、読み書きそろばんを寺子屋で学びましたが、
その際に使われた代表的な教材が、『節用集』をはじめとする往来物です。
『節用集』は、身のまわりの物の名前や行事、動植物、職業などを分類して記載した語彙集で、
初学者にとって最適な学習書でした。仮名と漢字にふりがなが付された版本が多く、
子どもたちにも読みやすい構成になっており、
文字に慣れる入り口として広く使われていました。
識字率を支えた出版文化と教材の工夫
例えば、江戸の町人の子どもが寺子屋で『節用集』を開き、
「火」「水」「米」「商い」といった基本語から学び始め、
徐々に応用語や短文に取り組んでいく姿が、当時の記録にも残されています。
これは単なる文字の習得にとどまらず、
言葉の意味や文化背景も同時に学べる教育だったのです。
このような教材の普及と内容の工夫により、
江戸時代の庶民の間に文字の読み書きが浸透し、
世界的にもまれな高水準の識字率を実現しました。
『節用集』は、知識への入り口としての役割を果たし、
庶民の生活や文化を支える「学びの土台」となっていたのです。
参考文献・リンク集
1. 蔦屋重三郎関連書籍・資料
- 鈴木俊幸 著『蔦重出版書目』(青裳堂, 1998)は、蔦屋重三郎が出版に関わった書目を網羅。国立国会図書館の所蔵リスト作成にも使用されています 名古屋刀剣ワールド+6戦国時代物語+6名古屋刀剣ワールド+6美術展ナビ+4国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)+4J-STAGE+4。
- 棚橋正博 編『黄表紙総覧』(青裳堂, 1986–2004)では、挿絵本(黄表紙)の版元・蔦屋の刊行物を詳細に整理 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)。
2. 学術論文・展覧会資料
- 蔦屋重三郎の浮世絵との関わりや版元印について詳述された記事:「蔦屋重三郎の浮世絵の見分け方」(ホームメイト名古屋刀剣博物館) 名古屋刀剣ワールド+2名古屋刀剣ワールド+2名古屋刀剣ワールド+2。
- 蔦屋出版物リスト(国立国会図書館デジタルコレクション内)には、狂歌本、洒落本、黄表紙などが掲載されています ウィキペディア+11国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)+11美術展ナビ+11。
3. デジタルコレクション(国立国会図書館)
- 国会図書館サーチで「蔦屋重三郎」で検索可能。オンラインで閲覧・DLできる蔦屋刊行の狂歌絵本や黄表紙などが多数リスト化されています ウィキペディア+4国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)+4J-STAGE+4。
- 古典籍展「和漢書の部」には、初期の「節用集」写本も紹介されており、近世以来の辞書出版の系譜をたどる資料として有益 note(ノート)+3国立国会図書館+3美術展ナビ+3。
4. ウェブ記事・解説
- 「春町と節用集重版について」(大和愛/Note)は、大河ドラマを通じて蔦屋と黄表紙文化を紹介した記事 名古屋刀剣ワールド+11note(ノート)+11note(ノート)+11。
- “鱗剥がれた『節用集』”事件(1775年)を扱ったドラマ回の解説記事。版木没収や海賊版問題など当時の出版権争いが記録されています 美術展ナビ+1service.orikomi.co.jp+1。
5. 展覧会図録・特設サイト
- 特別展「蔦屋重三郎コンテンツビジネス」公式図録(約400頁)は、喜多川歌麿や写楽など蔦屋関連の浮世絵・本を多数収録 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)+9特別展「蔦屋重三郎コンテンツビジネスの風雲児」公式サイト+9名古屋刀剣ワールド+9。
- 展示ツアーや関連グッズもオンライン販売中で、こちらも参考になります 特別展「蔦屋重三郎コンテンツビジネスの風雲児」公式サイト。
節用集に収録されている具体的な言葉
「節用集」に収録されている具体的な言葉には、
日常生活で使用される一般的な語彙、漢字の読み方
、漢文の読み方、和語、外来語などが含まれています。
具体的な例として、食べ物、動植物、道具、身体部位、地名、人名など
幅広いカテゴリの言葉が収録されています。
具体例
食べ物: 米、魚、野菜、醤油、味噌
動物: 犬、猫、馬、鳥、魚
植物: 桜、松、梅、竹、蘭
道具: 鍋、箸、筆、鋏、桶
身体部位: 頭、手、足、目、耳
これらの言葉には漢字の読み方や使い方、用例などが含まれており、
当時の日常生活や文化を理解するための貴重な資料となっています。
節用集の文化的な背景
「節用集」に収録された言葉は、当時の文化や生活習慣を反映しています。
その背景をいくつか紹介します。
食べ物
米: 日本の主食として古くから栽培され、食文化の中心を担ってきました。
米を使った料理や儀式など、日本文化に深く根付いています。
醤油: 日本料理の基本的な調味料で、発酵によって作られます。
江戸時代には広く使用されるようになり、料理の風味を豊かにしました。
動物
犬: 犬は古くから日本人の生活に密接に関わっており
、守護犬や狩猟犬として重要な役割を果たしました。
江戸時代には、犬をテーマにした物語や浮世絵も多数描かれています。
猫: 猫はネズミを捕まえる役割がある一方で、
江戸時代にはペットとしても人気がありました。
猫を描いた浮世絵や民話も多く存在します。
道具
筆: 書道や絵画に欠かせない道具であり、
江戸時代には職人が手作りで筆を製作しました。
書道は教養として学ばれ、
書の腕前が評価されることもありました。
箸: 食事の際に使われる道具で、
木や竹から作られています。
箸には、食文化や礼儀作法に関する意味合いが込められています。
身体部位
頭: 人間の知恵や思考の象徴とされ、
江戸時代の教育や文化においても重要な位置を占めていました。
手: 手は労働や芸術活動において重要な役割を果たし、
手作業の職人技術が高度に発展しました。
節用集の庶民の学びの場-寺子屋への影響
- 江戸時代の識字率向上に寄与し、商業活動の発展にも貢献しました。
- 近代の国語辞典(例えば『言海』や『大言海』)の基礎となる部分もあり、日本語辞書の発展に影響を与えました。
- 明治時代以降、近代的な辞書が登場すると次第に使われなくなりましたが、現在でも歴史資料として価値があります。
江戸時代の学びを支えた「節用集」— 寺子屋での活用と影響

江戸時代の寺子屋において「節用集」は重要な教科書として使用されていました。これは、学習者が日常的に使う単語や表現をまとめた辞書で、五十音順ではなくテーマごとに分類されています。そのため、子供たちが実際の生活で使う言葉や表現を学ぶのに非常に便利でした。
節用集の影響
- 識字率の向上: 節用集は、庶民の識字率を向上させるために大きく貢献しました。多くの子供たちが寺子屋で節用集を使って学び、基礎的な読み書きの能力を身に付けました。
- 文化の普及: 節用集は、江戸時代の文化や日常生活を反映しており、子供たちはそれを通じて日本の伝統や風習を学びました
江戸時代の子供たちと「節用集」— 学びの方法とその意義
江戸時代の子供たちは、寺子屋での学びの一環として「節用集」を用いていました。具体的には、次のような方法で学んでいました。
1. 素読(そどく)
素読とは、文章を意味を考えずに声に出して読む学習方法です。子供たちは節用集の漢字や単語を繰り返し声に出して読むことで、音やリズムを体得しました。この方法により、漢字の読み方や正しい発音を自然に覚えました。
2. 書写(しょしゃ)
書写は、手本を見ながら文字を書き写す学習方法です。子供たちは、節用集に載っている漢字をお手本として、正しい筆順や形を練習しました。何度も繰り返し書くことで、漢字を覚え、書き方を習得しました。
3. 読み書きの実践
寺子屋では、節用集に掲載されている単語や文章を使って、実際の手紙や文章を書く練習も行いました。例えば、子供たちは家族や友人に手紙を書く際に節用集を参考にし、正しい表現や言葉遣いを学びました。
4. 意味の理解
素読や書写を通じて漢字や単語を覚えた後、先生は子供たちにその意味や使い方を教えました。具体的な例を示しながら、日常生活での使用方法を説明しました。このようにして、子供たちは単なる暗記だけでなく、実際に使える知識として習得しました。
5. 繰り返しと継続
学習は一度で終わるわけではなく、繰り返しと継続が重要でした。子供たちは毎日少しずつ節用集を読み、書き、覚えることで、徐々に知識を深めていきました
鱗形屋の節用集の偽物事件とは?
鱗形屋は、大河「べらぼう」では作中で偽物の節用集を出版した業者として描かれています。
江戸時代には、人気の本が偽造・海賊版として出回ることが多々ありました。
特に、節用集のような実用書は需要が高く、
偽物も作られやすかったのです。
鱗形屋は、内容の誤りが多い粗悪な節用集を大量に流通させ、
これが後に大きな問題となりました。
大河「べらぼう」では、この偽物事件をめぐり、蔦屋重三郎(蔦重)が
どのように関わっていくのかが描かれます。
蔦重は出版業界の先駆者として、質の高い本作りにこだわる人物であり、
この事件を通して「本の価値とは何か?」
という問いが浮かび上がってくるのです。
節用集を見るには
1. 国立国会図書館デジタルコレクション
- 国立国会図書館デジタルコレクション では、公開されている江戸時代の「節用集」の古書を閲覧できます。
- 「節用集」と検索すると、いくつかの版が見つかります。
2. 大学図書館・公立図書館
- 国立・公立の大学図書館や大きな公共図書館では、
江戸時代の辞書類の資料として所蔵されている場合があります。 - 「節用集」関連の資料があるかどうかは、
各図書館のオンラインカタログで検索できます。
3. 博物館・資料館
- 江戸東京博物館や国文学研究資料館など、
日本の歴史や国文学を扱う博物館・資料館では、
特別展示や閲覧室で見ることができる場合があります。
節用集のオンライン閲覧方法
1. 国立国会図書館デジタルコレクション
国立国会図書館デジタルコレクション で「節用集」と検索し、閲覧可能なデジタル化資料を探す。
2. Google ブックス
Google ブックス で「節用集」と検索し、プレビューや全文表示が可能な書籍を探す。
3. HathiTrust Digital Library
HathiTrust Digital Library にアクセスし、「節用集」または「Setuyoshu」で検索。
4. 国文学研究資料館(Kokubunken)
国文学研究資料館 のオンラインアーカイブで「節用集」を検索。
まとめ
「節用集」は江戸時代の庶民が使っていた実用的な辞書であり、
日常生活や商業、教育に役立てられました。
言葉の標準化や識字率向上に貢献し、
日本の辞書文化の礎となった重要な書物です。
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の公式ホームページは、NHKの以下のページです。
また、最新情報は公式X(旧Twitter)アカウント(@berabou_nhk)でも発信されています。
さらに、音楽情報に関しては特設サイトが設けられています。

