平安時代の貴族・藤原道長は、
摂関家として権勢を誇り、
当時の日本を象徴する人物です。
しかし、その栄華の裏側には晩年の病苦があり、
特に糖尿病に苦しんでいたとされています。
彼の晩年の生活や病の苦しみや
壮絶な最期を知ると
藤原道長の人生は本当に幸せな人生だったのでしょうか?
考えさせられます。
藤原道長の晩年ー50歳以降に始まった体調不良
道長が体調不良を感じ始めたのは
50歳を過ぎてからとされます。
『小右記』にあるように、
彼は大量の水を飲んでのどの渇きを癒し
体重の急激な減少や視力の衰え、
さらには大きな腫れ物にも悩まされました。
糖尿病の典型的な症状が見られることから、
彼が糖尿病を患っていた可能性が
高いと考えられています。
道長の身に起きた変化は、単なる老化とは異なり、
体の不調が深刻だったことがうかがえますね
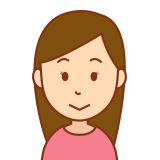
モミジは医者ではないのですが、上記の症状があれば現代人であれば多くの人が糖尿病を疑うのではないでしょうか

藤原道長の家族に見られる糖尿病遺伝的要因による糖尿病
藤原道長だけでなく、彼の家族にも糖尿病の症状が見られることから、
遺伝的要素が関与していた可能性が考えられます。
叔父や兄、甥、さらには孫も同様の症状で亡くなっており、
藤原家が糖尿病に対して
遺伝的な影響を受けやすい体質であったかもしれません。
藤原道長が極楽往生を願った晩年の歩み
晩年には栄華から信仰へ — 藤原道長が歩んだ極楽往生への道
平安時代の権力者・藤原道長は、現世での栄華を極めただけでなく、
来世の安寧を願い、極楽往生のための準備に力を注ぎました。
寛仁3年(1019年)、道長は度重なる病に見舞われ、
胸病や霍乱(急性胃腸炎)に苦しみ、
眼病で人の顔すら見えなくなるほどの体調不良に陥ります。
その中で彼は出家を決意し、信仰の道を歩み始めました。
晩年の藤永道長の法成寺の建立
彼は自邸に阿弥陀堂を建立し、これが後の法成寺へと発展。
法成寺は、阿弥陀如来像をはじめ、
金堂や五大堂などを備える壮大な寺院で、
道長の信仰心の深さを象徴しています。
晩年には、東大寺や高野山を巡拝し、
さらなる修行に励みました。
しかし、その晩年は病と苦しみに満ちていました。
現世の苦難を乗り越えながらも、
来世への準備を怠らなかった道長の姿は、
無常観を感じさせるものでした。
藤永道長の晩年の孤独ー愛した子供に先立たれる
身体の不調と並行して、道長は子どもたちの死にも直面します。
- 万寿2(1025)年:三女・寛子(敦明親王の女御)が27歳で病死。
- 万寿2(1025)年:六女・嬉子(敦明親王の妃)が19歳で早逝。
- 万寿4(1027)年:三男・顕信(出家して僧となる)が34歳で死去。
- 万寿4(1027)年:次女・妍子が病死。
このうち、顕信は若くして出家していたため、
父・道長も「早すぎる死」に大きなショックを受けたと伝えられています。
そして、次女の妍子を亡くしたとき、道長は『栄花物語』の中で
「老いた父母を置いていってしまわれるのか」と悲嘆に暮れたとされています。
栄華を極めた彼が、次々に愛する子どもたちを失い、
家族の喪失に苦しむ姿は、
権力の頂点に立つ人間の孤独を浮き彫りにしています。
藤原道長は、最も愛した家族たちの死を立て続けに経験し
孤独感と無常観を深めていきました。
藤原道長の晩年の糖尿病の合併症――“満月”はついに欠けた
晩年の道長は糖尿病の合併症に苦しみ、
次第に全身の衰弱が進んでいきました。
- 背中の腫れものが乳首や腕にまで拡がる
- 全身の震えが止まらなくなる
- 針博士・和気相成の診断では「毒が腹に入ったため、震えが止まらない」とされる
藤原道長の最期「大河ドラマ」では描けない頂点に立った男の凄絶な死
「波乱に満ちた最期」
藤原道長の死は、権力者としての波乱に満ちた最期を象徴していました。
11月中旬から病状が悪化し、失禁や下痢
背中の腫れ物に苦しむ日々が続きました
娘の彰子や中宮威子が見舞いに訪れるも、
汚れがひどく近づくことすら困難な状況でした。
道長のために後一条天皇や彰子が宗教儀式を行い、
多くの僧侶が集められるなど、宗教的救済が試みられました。
最期は孤独と救済の中で:藤原道長の死
万寿4(1027)年12月2日、医師・丹波忠明が背中の腫れものを鍼で突き、
膿を出した際、道長は激しい痛みを訴えて
昏睡状態に陥りました。
2日後の12月4日(1028年1月3日)、
道長は61歳でその生涯を閉じます。
晩年は孤独と病苦に満ちていましたが、
彼のために行われた数々の救済や、
見舞いに訪れた高貴な人物たちの姿は、
道長がいかに特別な存在であったかを物語っています。
藤原道長と藤原行成の不思議な縁ー同じ日に旅立つ
寛仁4年(1020年)12月4日、
平安時代を象徴する2人の人物が同じ日にこの世を去りました。
権力の絶頂を極めた藤原道長は
度重なる病の苦しみに耐えながら、
ついに62歳で旅立ちます。
そして、道長の側近であった藤原行成も同日、
体調不良の中で転倒が原因となり、
57歳でその生涯を閉じました
権勢を誇った2人が同じ日に世を去った偶然は、
平安の人々に大きな衝撃を与えたことでしょう。
彼らは果たして極楽浄土に辿り着けたのでしょうか。
藤原道長の最期が問いかける人間の限界
道長の最期は、華やかな平安貴族社会の光と影、その両面を浮き彫りにしています。
そして彼の死は、権力や富では抗えない「人間の限界」を私たちに問いかけ続けるのです。
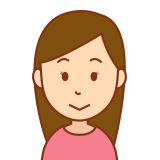
いずれにしても尋常な痛みではなさそうですね。
藤原道長は確かに最高権力者として、
全てを手に入れたようですが、
健康な体だけは手に入れることができなかったようですね。
でも、もしかしたら藤原道長にとっては健康より、権力の方が大事だったのかもしません。
権力が彼が生きた証なのですから。権力とはそれほど魅力的なものなのかも。
「藤原道長の人生」満月に見えた人生に“欠けていたもの”とは?
藤原道長の人生は、後世の私たちから見ると
「成功者の物語」として描かれることが多いです。
政治の実権を握り、家族の権勢を高め、平安貴族社会の“勝者”として君臨。
藤原道長の満月のごとき栄華の裏で――晩年に欠いたもの
しかし、晩年の彼が抱えていた“欠けたもの”は、健康と家族の安寧でした。
糖尿病という現代でも不治の病に苦しみ、
最愛の子どもたちに次々と先立たれるという苦難の連続。
道長は、権力の絶頂を謳歌しながらも、
健康を欠き、家族を欠き、心の平穏を欠いた人生だったのかもしれません。
「望月(満月)もいつかは欠ける」。
その象徴が、藤原道長その人の生涯だったのかもしれません。


